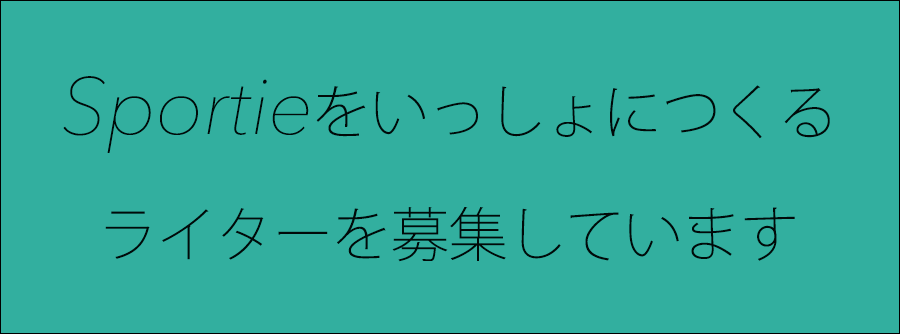筋トレ効果を高める「Deload Week」とは? 休息日との違いも解説
 DO
DO
筋トレ効果を高める「Deload Week」とは? 休息日との違いも解説
「筋肉は1日にして成らず」という諺は(たぶん)ありません。しかし、筋トレとはある程度の期間にわたって継続しないと意味がないものだとは確信を持って言えます。それもただ継続するだけではなく、負荷を徐々に増やしていくことが成果を得るためには不可欠です。
「強い子のミロ」いうキャッチフレーズを覚えているでしょうか? ネスレ社が製造販売する栄養ドリンクの商品名は、古代ギリシャのレスラー、ミロ(またはミロン)に由来するものです。
この人物には子牛を毎日担いで歩くことで筋力を鍛えたという伝説があります。子牛は日々成長し、昨日より今日の方が少しだけ重くなる。そうしてミロは徐々に重量負荷を増やしていった。筋トレの基本原則である「過負荷の法則」と「漸進性の法則」を説明するときによく用いられるエピソードです。
 “Milo of Croton, Holland Park” by redspotted is licensed under CC BY 2.0.
“Milo of Croton, Holland Park” by redspotted is licensed under CC BY 2.0.
残念ながら、ミロのような超人ならざる私たちは、ずっと右肩上がりで負荷を増やし続けることはできません。どうしても筋肉の成長が足踏みする停滞期が必ずやってきます。そのようなときに無理をしても効果は望めませんし、それどころか故障の危険すら生じます。
そこで、筋トレの健康的かつ継続的な成長を促すために、あえて意図的に負荷を大幅に減らす週(Deload Week)を定期的に設ける方法論を今回紹介します。
Deload Weekとは何か
「Deload」とはやや日本語に訳しにくい単語です。字義的な解釈では、以下のように分解できます。
- De-(取り除く・減らす)
- Load(負荷・荷物)
つまり、「負荷を減らす/取り除く」というのが直訳的な意味になります。筋トレの文脈では、挙上重量を意図的に軽くするという意味で使われます。
Deload Weekでは、筋トレの頻度や回数は大きく変えず、あえて重量負荷のみを前週の30~50%程度まで減らします。たとえば通常100kgで5セット5回を行っている種目なら、Deload Weekでは30~50kgで同じ回数・セット数を行うように調整します。
多くの筋トレ方法論で、このDeload Weekを4~6週間ごとに設けることを推奨しています。以前紹介した「5-3-1メソッド」もそのひとつ。こちらは4週のうち1週がDeload Weekに設定されています。
関連記事:筋トレで伸び悩んでいる人におススメの5-3-1メソッド
休息日(rest day)との違い
 バーのみ(20kg)でベンチプレスを行う筆者
バーのみ(20kg)でベンチプレスを行う筆者
Deload Weekは休息日(rest day)とはややニュアンスが異なります。休息日は「完全なオフ」のイメージで、筋肉への負荷を断つ日です。たとえば、よくある「筋トレを週3日行う」場合は、残りの4日は休息日ですので筋トレは行いません。その目的は筋肉・神経系の回復を図り、同時に筋肉の成長を促すことにあります。休息日は筋肉を刺激しません。
それに対して、Deload Weekでは筋トレそのものは継続します。ただし、負荷を大幅に減らすことで、疲労回復とトレーニング成果の維持を両立させることが主な目的です。筋肉への刺激を維持しつつ、フォームの再確認や可動域の拡張、モチベーションのリセットにもつながります。そうすることで、次週以降のパフォーマンス向上を狙います。
Deload Weekで本当に筋肉は減らないの?の疑問に答える研究
Deload Weekを導入するにあたって、技術的には難しいことは何もありません。ハードルはむしろ心理面にあります。
筋トレをしない人には理解しづらいことかもしれませんが、これまで100kgのバーベルを挙げていた人が、急に50kg以下で筋トレを終えることへの抵抗感はとても大きいのです。なにしろ、ふだんならウォームアップにも物足りないくらいの重量ですので。
Deload Weekでは、予定したセット数を終えても、いつものような筋肉の痛みはやってきません。”No Pain No Gain”(痛みのないところに成果はない)が信条の筋トレ愛好家は、これだけでジムを後にすることに躊躇します。
ついつい、こんなに軽いのなら回数を増やしてみよう、などと思ってしまいがちですが、それでは筋持久力を向上するためのトレーニングになってしまいます。あくまで、回数と頻度を同じレベルに維持したまま、重量だけを減らすことがDeload Weekの大原則です。
そんなことをしたら、せっかく鍛えた筋肉が減ってしまうじゃないか、という懸念はもっともです。個人的な主観を述べるなら、その心配は杞憂です。1週間くらい重量を半分に減らしても、翌週からちゃんと以前と同じかそれ以上の重量で筋トレはできます。
そんな私の体験談だけでは安心できないでしょうから、Deload Weekの効果・逆効果について調べた学術研究を2つ紹介します。
小笠原理紀氏、石井直方氏ら、日本人研究者たちが2012年に発表した研究(*1)では、連続トレーニング(24週間継続)と、6週間のトレーニングと3週間のDeload Weekを繰り返す周期的トレーニングの効果を比較しました。その結果、24週終了時に両群の筋肉のサイズ・筋力の総向上は同程度でした。つまり、Deload Weekには筋力を向上させる効果はないかもしれませんが、悪影響もまたないということになります。
ニューヨーク大学の研究者らが2024年に発表した研究(*2)は、観察期間を9週間とやや短く設定し、期間中筋トレをずっと継続したグループと間に1週間のDeload Weekを挟んだグループを比較しました。その結果、Deload Weekによって筋肥大や持久力の進展に悪影響はほとんどなく、最大筋力のみがやや低下する傾向が確認されました。
数値では測れないDeload Weekのメリット
 バーのみ(2kg)でバックスクワットを行う筆者
バーのみ(2kg)でバックスクワットを行う筆者
ここからはまた私見に戻ります。必ずしも科学的根拠に裏付けられているわけではありませんが、私が実感したDeload Weekのメリットについて述べたいと思います。
まず、精神的なリフレッシュ効果です。もっと重く、もっと多くと、負荷に追われ続けるストレスから一時的に離れることで、身体的にも精神的にも疲労がリセットされます。オーバートレーニング症候群(トレーニングによって生じた身体的・精神的な疲労が十分に回復しないまま積み重なり、常に疲労を感じる慢性疲労状態となること)への予防にもつながるでしょう。
軽い負荷で筋トレ動作をすることで、フォームと可動域の見直しができることもメリットのひとつです。重量や回数の限界に挑む筋トレを続けていると、知らず知らずのうちにフォームが崩れてきます。伸ばすべきところまで伸ばせず、あるいは曲げるべきところまで曲げられなくなりがちです。Deload Weekでは正しいフォームに集中しやすく、関節の動きや可動域の確認も行いやすくなります。長期的には筋トレ効果を伸ばす可能性が大きいのではないでしょうか。
まとめ
ある程度の期間、筋トレを継続して行っている人は、4~6週間に1回くらいの間隔で、Deload Weekを設定することをおすすめします。筋トレのボリューム(頻度、セット数、レップ回数)を変更せずに、重量を通常の30~50%に減らすことが原則です。
Deload Weekでは筋肉を完全に休ませるのではなく、意図的に軽めの刺激を与えることで、継続性を維持し、筋トレの長期的な成果に結びつけることを目的とします。
参照文献:
*1. Comparison of muscle hypertrophy following 6-month of continuous and periodic strength training
https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-012-2511-9
*2. Gaining more from doing less? The effects of a one-week deload period during supervised resistance training on muscular adaptations
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10809978/?utm_source=chatgpt.com