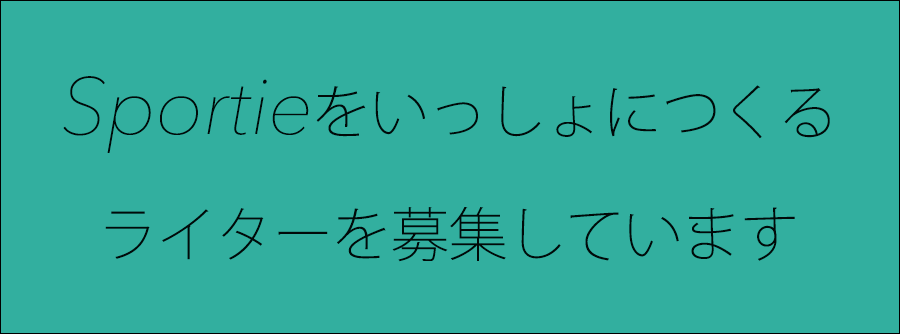カリフォルニアで真ん中レベルの高校野球とはどんな感じ? ー 日本人コーチが紹介する米国のスポーツ部活動その22
 WATCH
WATCH
カリフォルニアで真ん中レベルの高校野球とはどんな感じ? ー 日本人コーチが紹介する米国のスポーツ部活動その22
5月中旬のある日、私がアメリカ・カリフォルニア州のラグナヒルズ高校で野球部のコーチという仕事を始めてから6年目のシーズンが終了しました。2月から約3か月間のリーグ戦で、我がチームは27試合を戦って14勝13敗。リーグ戦上位半分ほどが進出できるプレーオフのトーナメントにギリギリで滑り込み、1回戦を突破したものの、2回戦で敗退しました。
カリフォルニアはアメリカでもっとも野球が盛んな州のひとつです。州内の高校野球は10の地区、9つの競技レベル別ディビジョンに分けられています。我が校が所属するのは、ロサンゼルス市とサンディエゴ市を除く南カリフォルニア地区、今シーズンのレベルは第5ディビジョンです。ちょうど真ん中くらいのレベルで勝率がほぼ5割ですので、我が校はアメリカの高校野球でまずまず平均的なチームだと言えるでしょう。
ドラマチックな幕切れ
 試合前の国家斉唱。
試合前の国家斉唱。
敗れたプレーオフ2回戦で最後のバッターになった選手は最終学年でした。私は彼が1年生の頃からよく知っています。こちらの高校は4年制ですので、14歳から18歳までの4年間、まるで子どものような顔をしていた彼が青年と呼ぶべき姿になるまで成長してきた様を、野球を通して見てきました。
最終回、ツーアウト、フルカウントから明らかな高めのボール球に思わずバットが出てしまい、中途半端なハーフスイングでの三振で試合が終了。彼にとっては悔やんでも悔やみきれない、高校野球最後の打席になりました。ヘルメットをベンチに叩きつけ、涙を堪えて、それでもすぐに試合終了の挨拶の列へ走っていきました。
彼が選んだ背番号12は次のシーズンからは他の誰かがつけるでしょう・・・・なんて、まるでユーミンの名曲『ノーサイド』のような感情過多に陥ってしまうほど、アメリカの高校野球も日本のそれと同じくらいドラマチックな要素に満ちています。同じスポーツを同じ年齢の少年たちがするのですから、国が違っても共通するものが多くあるのは当たり前なのかもしれません。
しかし、高校野球を成り立たせている制度や仕組みという側面から見ると、日本とアメリカではかなり事情が異なります。前置きが大変長くなりましたが、それが今回の本題です。
アメリカの高校野球事情:改革を進める日本へのヒント
 プレーオフ2回戦の観戦を呼び掛ける校内ポスター。
プレーオフ2回戦の観戦を呼び掛ける校内ポスター。
日本の高校野球は一般的な人気や知名度ではアメリカよりはるかに上を行きます。夏の甲子園大会はもはや国民的な伝統行事ともいえるでしょう。その一方で、近年は選手の健康管理や競技環境の見直しをめぐる議論が活発になってきました。
改革案それぞれには賛否両論がありますが、実はその多くはアメリカの高校野球ではすでに広く実施されている制度でもあります。むろん、日米で異なる事情も多々ありますし、アメリカの制度すべてが優れているわけでもないと思います。しかし、制度変更を検討する際に実際の先行例として捉えるならば、アメリカの高校野球事情を参考にすることはけっして無駄ではないと私は思います。
具体例を挙げると、
- 高野連は1週間に500球以内という投球数制限をルール化しましたが、アメリカではそれとは比較にならないほどの厳しいルールが以前から実施されています。
- 7イニング制の導入は現場の選手や指導者からの反発が強く、あのイチローさんも「絶対にやってほしくない」と発言していますが、アメリカの高校野球は以前から7イニング制です。
- 甲子園大会とその予選は1敗すると大会敗退が決定する勝ち抜きトーナメント方式で行われるため、勝利偏重主義の弊害や試合経験の格差が生じることが指摘されていますが、アメリカの高校野球はリーグ戦が中心です。前述した通り、プレーオフはトーナメント形式ですが。
関連記事:アメリカの高校野球:安全に野球を楽しむための工夫とは -日本人コーチが紹介する米国のスポーツ部活動その20
さらには、低反発の金属バットや熱中症対策など、日本の高校野球でも導入が始まっている、あるいは検討されている安全への取り組みはアメリカでも同様です。
アメリカの高校野球は、制度設計の参考になるだけでなく、日本の高校野球の「強さの源泉」がどこにあるのかを再考する手がかりにもなるでしょう。
むろん、私などがあらためて意見を述べるまでもなく、日本の高校野球界はすでに改革に取り組んでいます。2024年に本格始動した『Liga Futura』は、甲子園一辺倒主義からの脱却を掲げた、新しい育成・強化のためのリーグ戦の枠組みとして注目されています。
背景となるスポーツ文化の違い
 フラトン高校の横断幕には1919年度カリフォルニア州チャンピオンとある。
フラトン高校の横断幕には1919年度カリフォルニア州チャンピオンとある。
アメリカの高校野球も長い歴史を持つ。
野球に関わる議論とは別に、スポーツ全体に目を向けると、日米でもっとも大きな違いであると私が感じるのは、シーズン制と複数スポーツの掛け持ちについてです。
アメリカでは、子どもから大学に到るまで、スポーツは季節ごとに行われることがほとんどです。そのため、同じ選手が秋はフットボール、冬はバスケットボール、春は野球と、複数のスポーツを掛け持ちすることは珍しくありません。私が指導する高校球児の約半数も複数スポーツを行っています。
関連記事:クロストレーニングのススメ。アメリカに万能型アスリートが生まれる理由
むろん、野球一本に集中して厳しく鍛え上げるスタイルにも良い点はあります。反復練習は技術習得に欠かせないからです。その一方で、身体的な故障や精神的な負担のリスクが高まることも指摘されています。
若い世代の健康や将来を考えると、スポーツ全体でシーズン制を導入し、かつ複数スポーツ経験を可能にする環境を整えるべきではないでしょうか。そのうえで○○一筋に頑張りたいという人にはその道を選んでもらえばいいわけですし。
スポーツをシーズン制に分ける最大のメリットは、個人レベルではさまざまな経験ができること、スポーツ界全体では個々の競技人口を増やせることではないかと思います。
よく野球人気低下の原因としてサッカーの人気上昇が挙げられることを、私はつねづね不思議に思っています。ひとりの選手が野球とサッカーの両方を行えば、それぞれの競技人口は増えるからです。スポーツをやる側だけではなく、見る側についても同様です。
つまり、本来であれば、あるスポーツと他のスポーツは競い合う関係ではなく、互いにスポーツ文化全体を豊かにする存在として共存できるはずなのです。どれかひとつを選ばせるのではなく、複数スポーツを楽しむ選択肢がもっと当たり前になれば、スポーツ全体の裾野はさらに広がるのではないでしょうか。